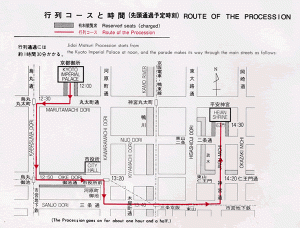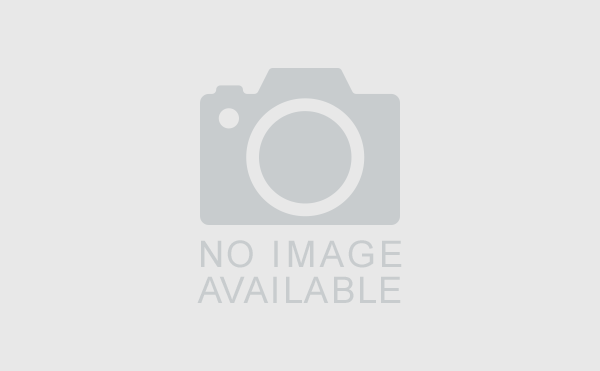悠久深遠
一大歴史風俗絵巻 「時代祭」 10月22日
御所出発12時 雨天順延... だそうです。 ぶひッ。
「明治28年、遷都1100年に沸く京都で「第四回内国勧業博覧会」が開催されました。この時、京都はパビリオンとして平安宮大極殿(だいごくでん)の5分の3の模型を建てましたが、その素晴らしさが評判となり、博覧会終了後も『残してほしい』という保存運動が起きました。
そこで、この模型の大極殿をそのまま神社として残す事となり、『平安神宮』が誕生いたしました。神社が誕生しますと祭礼(祭り)が必要となります。そこで多くの市民が、この新しい神社のための祭発足に参加し、一大時代仮装行列が考案され『時代祭』が生まれました。古くから都であった京都では、古時代の衣装も多く残っておりましたので、短期間で各時代の装束を揃える事も可能でした。そして、遷都1100年にちなんで、桓武天皇が長岡京から遷都されてきたと伝えられている10月22日が祭礼日に決まりました。
なお、桓武天皇の平安遷都は延暦13年(794)で、正確には明治28年は遷都1101年になります。祭礼の行列は、この時から、平安時代から明治維新までの装束に扮するものと決められ、当初、6行列が古い時代から順に巡行しておりましたが、大正時代に入り、『明治維新から平安時代へと時を遡ってパレード』するという、当時では、人々を驚かせる発想の転換を経て、現在では18行列がパレードしています。」(京都ガイドブックより)
(以上内容及び写真は京都ガイドより)
この祭りは、京都の歴史と文化に対する誇りを感じさせてくれる祭りと言われています。
但し、私の印象は、当日雨の日が多かったことです。
一般民家で私が知っている中かで一番古いのは築後約350年の家で、北区等持院にあります。
現在、経済的に急成長している中国、インド。日本はこの国から文化、芸術、経済など大きく恩恵をうけている隣国です。歴史も古くからあり、畏敬の念を禁じ得ません。高々200年で経済発展したというだけで慢心は排すべきでしょう。共生を探りながら発展を考えていかなと。